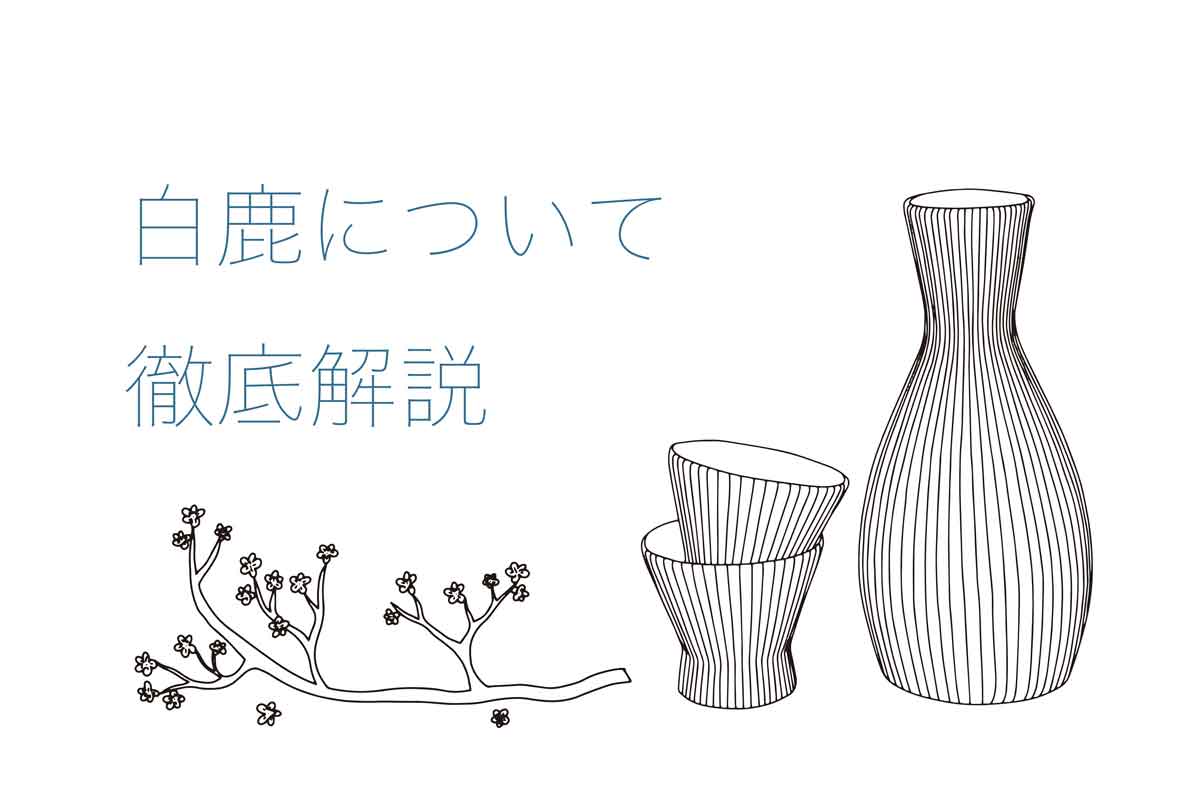
「日本酒50選シリーズ」は、「〇〇の日本酒を徹底解説!味の特徴は?どんなこだわりがあるの?」と題して、様々な銘柄や酒蔵を紹介するシリーズ記事です。
これまでの記事やこれからの記事はこちら、「おすすめ日本酒50選を徹底解説!味の特徴は?どんなこだわりがあるの?」に書いてありますので、ぜひ読んでみて下さいね。
No.25は「白鹿(はくしか)」です!
はじめに
白鹿(はくしか)は兵庫県西宮市の辰馬本家酒造から販売されている日本酒で、海外の数々のSAKEコンクールで賞をもらっているほど高い評価を受けています。
辰馬本家酒造は350年以上の歴史がある酒蔵で、白鹿は伝統の技で育てられた日本酒なのです。
しかし、辰馬本家酒造は伝統におごることなく、常に新しいおいしさを追求する姿勢を崩しません。
常に時代の最先端を進むという精神のもと、最新の機械を導入したり、バイオテクノロジーを応用するなどして酒造りを行っています。
今回は、そんな酒蔵で作られている白鹿の魅力を、名前の由来や味の特徴を交えながら紹介していきます。

【今なら期間限定で、初回送料0円!】
気軽にワインと本格的なペアリングが楽しめるワイン通販「the new(ザ・ニュー)」
土地に恵まれて誕生した白鹿
白鹿を製造している辰馬本家酒造は、日本を代表する酒どころ灘五郷(なだごごう)に酒蔵を構えています。
灘五郷は酒造りに最適な水、米、風土がそろった場所です。
白鹿には、酒を仕込む水に「宮水」が使用されています。
宮水とは、兵庫県西宮市の一部の地域から湧き出る水で、室町時代から「宮水を使った酒は絶品」と言われてきました。
宮水はミネラルを豊富に含む硬水で、酵母の発酵を助けるリンが多く含まれているのが特徴です。
さらに、酒の味を悪くする鉄分がほとんど含まれていません。
まさに、酒造りのためにあるかのような水なのです。
白鹿の銘柄は数多く出ていますが、香りが豊かですっきりと飲みやすい特徴があり、これは宮水のおかげと言われています。
日本酒によく使われる「山田錦」は、兵庫県で誕生したお米です。
山田錦は今では日本酒の原料としてメジャーですが、もともとは灘五郷の酒蔵のために開発された品種です。
白鹿に使われている山田錦は、契約を結んだ特定の農家で作られた上質なものになります。
このように信頼できる農家だけの米を使っている点にも、酒造りのこだわりが見えてきます。
白鹿は材料だけでなく、土地にも恵まれていました。
酒造りには、蒸した米を冷ます「放冷」という工程があります。今では機械で行われる作業ですが、昔は麻の布の上に米を広げて冷ましていました。
それでも、自然放冷では時間がかかり、ホコリや雑菌で米が汚れる心配があったのです。
ところが白鹿の場合は、六甲山系から吹き降ろす冷たく乾いた風が、素早い放冷を手助けしてくれたのです。
辰馬本家酒造は、西宮の風土も酒造りに取り入れてきたことがわかります。
白鹿の由来と白鹿記念酒造博物館
白鹿の由来は、次の中国の故事からとられています。
唐の時代、皇帝の宮殿に一匹の白い鹿が迷い込んできました。
仙人の王旻(おうびん)は、その鹿を千年生きたと見てとります。
その証拠として、鹿の角には宜春苑(ぎしゅんえん)の名が記された銅牌が結びつけられていました。
宜春苑は、唐から1000年以上も前の漢の時代に実在した皇帝です。
現皇帝は、この白鹿を縁起がいいと喜び、終生大事に扱ったと言われています。 縁起がよいということで、白鹿の名前が銘柄に使われるようになりました。
そこには、千年以上生きた白鹿のように、多くの人が毎日を楽しみながら長生きしてほしいという願いも込められているのです。

辰馬本家酒造は、白鹿の歴史や魅力を知ってもらうために「白鹿記念酒造博物館」という博物館を設けています。
1982年に開館しましたが、阪神淡路大震災の際に全壊。現在はリニューアルされ、白鹿の文献や日本酒に関する美術品を展示している記念館と、昔の酒造りの道具や技について知ることができる酒蔵館の2棟で営業しています。
記念館は年5回ほど特別展を開いており、生涯桜を描き続けた芸術家 笹部新太郎の作品を展示する「笹部さくらコレクション展」や、福の神をテーマにした「堀内ゑびすコレクション展」などを楽しむことができます。
酒蔵館ではスタッフによるガイドツアーも行われており、白鹿に対する理解をより深めることが可能です。
また、博物館では定期的にさまざまな子供向けイベントも行われていて、大人だけでなく子供も楽しめるようになっています。
手間暇かけた四段仕込みの白鹿
手間暇かけた四段仕込みの白鹿 醸造タンクに水、米、米麹、酒母を加えてもろみを作ることを「仕込み」と言います。
一度に大量の材料を酒母に投入すると、酵母と酸が薄まって発酵が追い付かず、雑菌に汚染されるリスクがあります。
そこで仕込みは、4日間に3回に分けて材料を投入していくのが普通です。
初日の仕込みを「初添え」といい、まだアルコールの生成はありません。
そのため、空気に触れる面積が大きくなれば雑菌繁殖の危険も大きくなるので、初添えには小さな容器を使うところもあります。
2日目は「踊り」といって、酵母を増殖させるために仕込みをお休みします。
踊りをはさんでから、3日目に「仲添え」、4日目に「留添え」という仕込みを行うことで、醸造がうまく進むのです。
このように3回に分けて仕込む方法を「三段仕込み」と呼び、多くの日本酒がこの手法で作られています。
白鹿のなかには、この三段仕込みの後にさらに追加の仕込みを行う「四段仕込み」によってつくられる銘柄があります。
三段仕込みの後に、うるち米やもち米、水、酵素などを加えることで、日本酒の甘みが増す効果があります。
白鹿の場合は、四段仕込みでもち米を投入して、味にふくらみを持たせています。

白鹿の四段仕込みの酒は、純米酒の「特撰 黒松白鹿 純米 もち四段仕込」と本醸造酒の「特撰 黒松白鹿 本醸造 四段仕込」です。
純米酒のほうは、大正時代の杜氏 梅田多三郎がつくった酒を手本にしながら、それを超えるものを目指した酒です。
味はやわらかく、上品な甘みがあると言われています。
国内での評価も高く、2013~2015年の3年連続モンドセレクション金賞に輝きました。
本醸造酒の四段仕込みは、甘みと酸味のバランスが取れた味わいで、ぬる燗にするとさらに甘みが際立つという評判があります。
白鹿で乾杯しよう

白鹿は、江戸時代から続く伝統の技とハイテク技術によってつくられている日本酒です。
蔵元の辰馬本家酒造は、灘五郷という酒造りに適した土地のアドバンテージを生かしつつ、技術を継承して人材を育てていくことで日本を代表する酒造メーカーとなりました。
白鹿の製造と並行して、白鹿記念酒造博物館を設立したり、海外の品評会に参加するなど日本酒文化の普及に努めています。
白鹿は日本料理だけでなく洋食にも合う日本酒です。
白鹿銘柄のラインナップはたくさんあるので、自分にぴったりの白鹿を探して、晩酌のお供に選んでみるのもおすすめです。
いかがでしたでしょうか。今回は、「白鹿の日本酒を徹底解説!味の特徴は?どんなこだわりがあるの?」について書きました。ぜひ白鹿を飲みながら、もう一度読んでみて下さいね。
次回は「白雪」です!白雪にも色々な種類があり、米、水、麹、酵母のすべてにおいてこだわり抜いた品質を追求しています。その造りのこだわりを認められ、1893年にシカゴの世界万国博覧会で金牌を受賞しました。
記事はこちら>>白雪の日本酒を徹底解説!日本最古の銘柄の味わいの特徴やこだわり - theDANN media
theDANN mediaでは、世界中のワインと料理を掛け合わせた新しいワインのストーリー「the new(ザ・ニュー)」をご提供しております。

【今なら期間限定で、初回送料0円!】
気軽にワインと本格的なペアリングが楽しめるワイン通販「the new(ザ・ニュー)」
ソムリエ様が厳選した2000円から購入できる赤・白・泡のワインと、ワインにぴったりなお料理のレシピ(無料)をお楽しみいただけます。
レシピ本は、ワインソムリエ様とフードコーディネーター様が考案した本格的なお料理。
ワインとのペアリングによって、素晴らしいマリアージュが堪能できます。
いつものディナーが、まるで旅行先でふと入ったレストランにいるような楽しいひとときになるでしょう。
パートナーの方やご友人の方と、気軽にペアリングを楽しめます。
ぜひ、the newによる新しいワインのストーリーをお楽しみください。